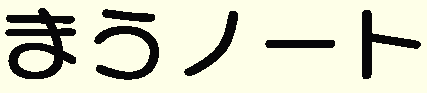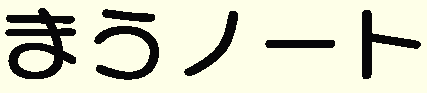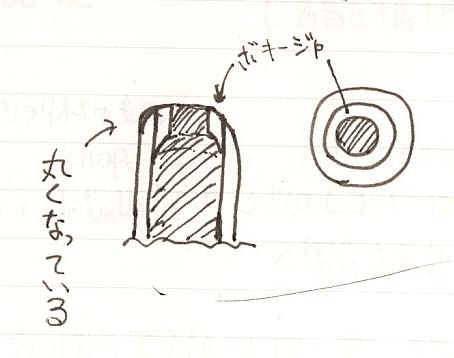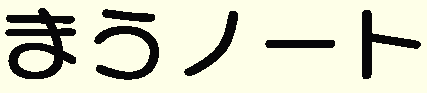
2.各地のサンポーニャ
底のふさがった管を並べた楽器、パンパイプ。
一列のものはアンタラと呼ばれる。
日本にも正倉院宝物倉に排籥の名で伝わっている。
漢字も楽器の形を示している。昔の日本とアンデスは近かった。その1。
出光美術館の大貫さんによると、モチェ文化では、
高貴な人の楽器として頭のわきに副葬されたという。
アマゾンを起源として、アンデスを昇りながら伝幡したと言われている。
(チリワノス)
BC1200にポトシ北部で粘土製アンタラ(5〜6管)が使われている。
(カブール氏所有)プレコロンビア期である。
Puno〜LaPaz間のティティカカ湖周辺で特に発達した楽器である。
サンポーニャの分類
☆7〜8管 低音+1ずつ加 ○5音 アンタラ
☆共鳴管なし─開鳴管─オクターブ管─オクターブ開鳴
☆調 Em E♭m ・・・他
☆管の素材 葦、素焼き、羽
Zampon~a Cromatica クロマティック・サンポーニャ (3列)
従来のサンポーニャでは、半音の多い曲を吹くのは困難であった。
サンポーニャ奏者のFernando Jimenes氏が♯が、
複数の曲を(♯3ヶの曲)弾く必要に迫られて作った楽器。 '80年代後半?
9(手前)─10管+アンタラ
F♯の上にFが位置するのが一般的。(手前のEの2つ上がFの3段)
この半音要の一列の管は単にANTARAと呼ばれていた。
なお、ヒメネス氏が以前作っていたサンポーニャは、管の太さ、
音色が整っていて6─7管の間にスペーサーも入れ
吹き易く固定してある。価格も高い分、良い楽器を作っていた。
なお、日本の瀬木貴将君も、3列の発案者だと言っている。
サンカの3列は、ルミリャフタが1988年使用している。
半音管の並びの違うものがある。
3列クロマティック・サンポーニャの例
Re♯ Fa Sol♯ La♯ Do♯ Re♯ Fa Sol♯
\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
Re Fa♯ La Do Mi Sol Si
\ / \ / \ / \ / \ / \ /
Mi Sol Si Re Fa♯ La
1990年代のマルタ
80年代後半から、90年にかけて、マルタは管数が増えてきた。
音楽の発展と共に、使いやすく変化している。
6─7管は、コチャバンバの肉厚以外は、少なくなってきた。
トヨスも同じ様な傾向になりつつある。サンカは変化していない。
B G E C A F♯ D 低音側
\ / \ / \/ \ / \ / \ / 6─7管
A F♯ D B G E
D B G E C A F♯ D
\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 7─8管
C A F♯ D B G E
D B G E C A F♯ D B G
\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 9─10管
C A F♯ D B G E C A
A F♯ D B G E C A F♯ D B G
\ / \/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 11─12管
G E C A F♯ D B G E C A
2列を challaと呼ぶ?
Ch'alla sicu 2列全音階の6−7管の最も一般的なもの。
Chaka sicuとPunoの本には書いてあった(Sicu o Zampon~a
P34)
その倍音管付をchara sicuと書いてある(J'aktta sin~a 1A,P4,l1)
アイマラ語でサンポーニャをSicuと言い、1612 L・Bertonioの
アイマラ語辞典ではSicoと読んでいる。・・・Sico Phusatha シコを吹く
Sicuは(Punoの本では)Tikuとも呼び、Tin-Kull(Si-Kull)が語源。
ティー、又はシィーと鳴るものといったところか。
組のうち管数の少ない方を IRA・・・主、又は雄
多い方を ARCA・・・従、又は雌 と呼ぶ
西語Zampon~aの語源はZampon-Un~a。詳細不詳。
最近多くなったEm用にセットしたものを、
セグンダ・タキーニャ(第2タキーニャ)
昔のレコードに多かったE♭m用を、
プリメラ・タキーニャ(第1タキーニャ)という。
形状を表現するのに「不等辺台形」と書いてあった。
「リ」のサンポーニャ (Zampon~a En Sol)
Re Si♭ Sol Mi♭ Do La Fa 7管
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Do La Fa Re Si♭ Sol 6管
高← →低
Gmの曲用である。
参考 Kjarkas Nin~o de America
「ゼ」のサンポーニャ (Zampon~a En Re)
La Fa Re Si♭ Sol Mi Do La
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sol Mi Do La Fa Re Si♭
Dm調の為の組。レのサンポーニャ。
コチャバンバ県のグループ(カルカス、グルーポ・アマル等)で
耳にすることが多い。
Zampon~a Cochabambina (Tipo Kjarkas)
最近のスタイルだと思うが、
コチャバンバのカルカスの工房で作っているスタイル。
管は肉厚のBambuで、中型のサンカの低音の方や大型のトヨスの吹き口は
ボキージャ(Boquilla)をつけてあるので、音は出し易いが、全体が重くなり、
音の線がはっきりしない。管によって音色にバラつきが出やすい。
管径(内径、外径)を均一にしないと音が出にくいなど欠点もあるが、
頑丈で使い易い。
横幅が大きくなる分トヨスになると吹けないくらい大きい。
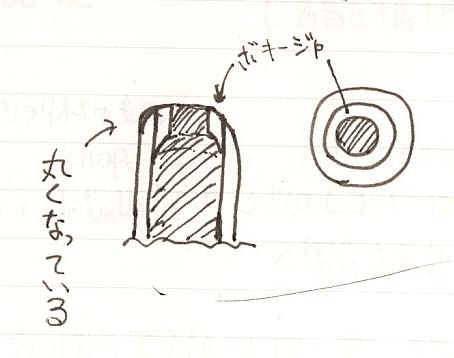
3.ミスティ スィク
まうノート・トップ